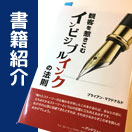今回ご紹介するのは、「ストーリー作り」「脚本」の書籍です。
株式会社ボーンデジタル様より献本いただきました。
「観客を惹きこむインビジブルインクの法則」ブライアン・マクドナルド著
読者が夢中になる物語を考えるには?
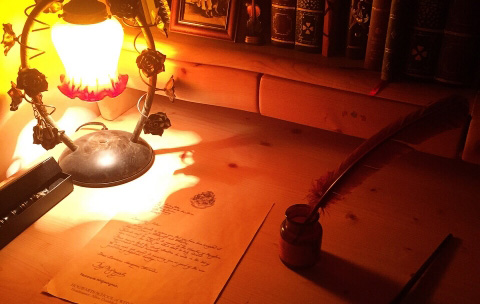
さてストーリーを考える時に、いったいどんなことから考えればよいのでしょうか。
これは、二次創作などで作品を作る時にも必ず必要になります。
漫画でも小説も時間の流れを含む作品はストーリーが必須です。
インビジブルインクとは何か
ストーリーを評価する時はセリフや文体について語られることが多いのですが、それらは「ビジブルインク」というべきものです。ビジブルとは容易に「見える」ことです。
起きる出来事の順序、語り手のメッセージを伝えるために欠かせないできごと、キャラクターがとる行動の理由といったもの、すべてを考えるのがストーリーテラーの仕事です。
「観客を惹きこむインビジブルインクの法則」
これが「インビジブルインク(見えないインク)」です。
そう呼ぶのは、読者や鑑賞者にとって、簡単には見えないことだからです。
しかし、それら「インビジブルインク」がストーリーに与える影響は絶大です。
つまり、先に書いたようにはっきり見ることはできません。
その使い方を学べば、作品は洗練されます。
この書籍の中では実際にストーリーを構成する要素をどう理解し、そのように作品に活かしていくかが紹介されています。
またプロのように、読者を夢中にさせる作品にするために何が必要かが具体的な例を交えて解説されています。
その中のいくつかを紹介します。
ストーリー向上のための7つのステップ

冒頭ではストーリーを構成する基本的なステップを紹介しています。
この7つをベースにすれば少なくとも流れ自体が破綻したりすることはありません。
- むかしむかし
- 毎日
- ある日
- そうして
- そうして
- そしてついに
- 以来ずっと
こうして並べてみるとどこかで見たような、というか懐かしいフレーズですよね。
具体的にそれぞれのステップにどのような役割があるのか、次で紹介していきます。
むかしむかし・毎日
主人公の日常を語るパートです。ここは後にストーリーを理解するうえで必要な情報を伝えます。
ストーリーのセットアップを行います。
ここが上手くいかないと第3パート「ある日」にうまくつながりません。
ある日
むかしむかし・毎日で繰り返してきた日常が途切れます。
書籍の中では「インサイティング・インシデント(引き金となる出来事)」と表現されています。
例えば浮気をする男女についてのストーリーであれば二人の出会いかもしれません。
また、家賃を払えないほど貧しい女性がいたら、彼女が100万円を見つけたところで終わります。
ここは、幕あい、プロットポイント、ターニングポイントなどと呼ばれます。
もっとも変化が大きなところでこの幕は終了します。
そうして
第4番目の「そうして」では、「ある日」で起った出来事に、どのようなことが出来るのかを描きます。
例えば第一幕で癌に侵されていた場合、ここでは、その病魔にどう立ち向かうのか、あるいは、あきらめるのか、主人公は何かの行動を起こします。
そうして
2度目の「そうして」はたいてい最も長く、ストーリのメインを構成します。
読む人を集中させておくために、半分に分けてもよいでしょう。
先ほどの癌を患った主人公の例であれば、癌と診断された、自分を大切に思ってくれる人たちを遠ざけます。しかしここで、彼は生きたいと思わせる出来事が起こります。そして生きるために治療法を見つけようとします。
そしてついに…
ここはストーリー終盤の始まりです。ここで起きる出来事がクライマックスにつながっていきます。
癌を患った主人公であれば、運命に従い、迫りくる死を受け入れるでしょう。難しい治療法を探すのはやめて残された時間をを家族や友人と大切に過ごします。
以来ずっと…
クライマックスの後には、結末と呼ばれる1~2つの短いシーンが続きます。
以来ずっとの例としては「それからずっと幸せに暮らしました」がもっとも馴染みがある結末でしょう。
クライマックスの後は詳しく踏み込まずに主人公のその後の人生がどうなるかを示唆する程度にします。
癌を患った例では、その人は恐らくなくなりますが、死に立ち向かった彼の勇気は残された人々に受け継がれていくかもしれませんし、彼は自分の作品を通じて生き続けるかもしれません。
それぞれのステップの名称を間に余白を残して書き出してみます。そこからまず、簡単なストーリを描いてみます。
何となく物語に深みがなくて物足りないかもしれません。
それを次の項目でいくつか説明します。
ストーリーに深みを持たせるテクニック
骨組みを伝える
ストーリーを形作る骨組みとは、「(作品を通じて)読者に伝えたいこと(=テーマ)」です。きちんと骨組みが構成された物語は記憶に残ります。
ミダス王の話の例が紹介されています。欲深いミダス王は振れたものがすべて黄金に代わることを望みます。しかし、愛する娘に触れて、彼女が黄金になってしまったことで、自分の欲深さを後悔します。このストーリーでは、お金より重要なものがあることを教えてくれます。
また己の力を過信して天に届く等を建造しようとしたニムロド王の話では、髪が全労働者にそれぞれ異なる言語を与え、互いにコミュニカーションんを取れなくしたとき、ニムロド王は自分の身の程を知ります。これは人々のうぬぼれを戒めることがテーマです。
こうした骨組み(テーマ)はもちろん言葉で伝えることもできますが、骨組み自体がドラマ化されることでより共感されるものになります。
儀式的苦痛
ストーリーが進むにつれて、キャラクターが変化していくことがあります。
しかし、急に変化するのは不自然です。人が成長したり、変わることは簡単でないことは読者も日常でよくわかっているからです。
そこで使われるのが「儀式的苦痛」です。
それでは「儀式的苦痛」とは何でしょうか。
例えば、部族などの成人の儀式では抜歯や刺青を行うことがあります。これらは苦痛を通じて大人になる事を意味します。
また、成人の儀式に限りません。成長するには精神的な苦痛を乗り越える必要があります。
書籍では名作「ジョーズ」について解説されています。
水を恐れる男が、サメと闘うという儀式的苦痛を経て変わります。それにより彼自身も救われます。
優位な立場
有名なアルフレド・ヒッチコック監督の言葉を引用して、ここでは「サスペンス」と「サプライズ」の違いを説明しています。
二人が会話しているテーブルの下のセットされていた爆弾が突然爆発することは観客にとってサプライズです。
一方、観客がすでにテーブルの下にセットされていることを知っていて、会話している二人に危機を知らせたい、そんな状態がサスペンスになります。
このように優位な立場とは、スクリーン上のキャラクターが知らないことを観客が知っている時のことです。
ヒッチコック監督のように、シリアスなシーンでも使えることもありますが、一方コメディで使うこともできます。
例えばキャラクターが熟睡していることを観客が知っていて、それを死んでしまったと嘆き悲しんでいる他のキャラクターがいる場合、その悲嘆が激しければ激しいほど、観客には滑稽に見えるかもしれません。
この「優位な立場」は使い方次第で観客を怖がらせたり、楽しませることができます。
まとめ
今回は「観客を惹きこむインビジブルインクの法則」から【ストーリー向上のための7ステップ】、ストーリーの深みがさらに増す【骨組みを伝える】【儀式的苦痛】【優位な立場】を紹介しました。
この他にも、創作、ストーリー作りに役立つテクニックや事例が多く紹介されています。
いつもストーリー作りに悩んでしまう、とか書(描)いているうちにストーリーが破綻していることに気が付いたり、あるいは面白いのかどうか自信がなくなってしまう、といった方にはぜひ読んでいただきたい書籍です。
また創作だけでなく、物語を観客として楽しむときにも「インビジブルインク」を知っていて損はありません。さらに深く物語を楽しむことが出来るかもしれません。
「観客を惹きこむインビジブルインクの法則」ブライアン・マクドナルド著